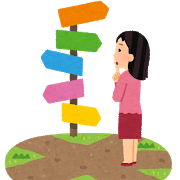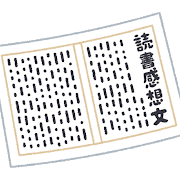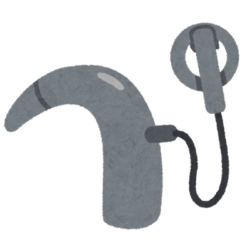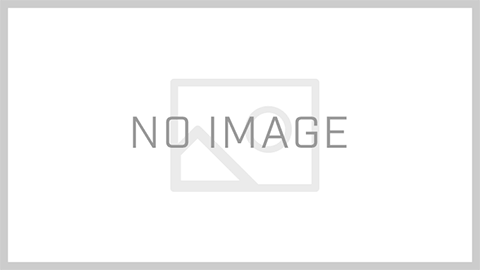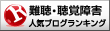「先天性の難聴の早期発見、早期補聴、早期療育の理想は、0か月、3か月、6か月」と言われています。最近は療育まで、最短3か月という地域もあるそうです。
産院で退院前に新生児スクリーニング検査でリファーと伝えらえた時。
(確定診断ではないので、再検査に希望をもってくださいね。再検査でパスすることもあります。)
元気に生まれたものとばかり思っていた家族にとっては信じられない気持ちだと思います。なかなか受け入れることも困難です。
でも、「聞こえない」ということが確かになった時は、早期補聴(補聴器装用)へ動いてくださいね。
行動を進めるのは大変つらいことですが、お子さんによっては補聴器で聞こえる子もたくさんいます。
お子さんの補聴器装用=音の世界の始まりです。
補聴器装用する前も、できることはたくさんあります。
お母さんの声でたくさんあやしてあげてください。
お父さんの声で包んであげてください。
お兄ちゃんお姉ちゃんの笑い声を聞かせてあげてください。
おじいちゃんおばあさんに甘やかしてもらってください。
そうです。聞こえる赤ちゃんと同じです。
短い新生児期を楽しんでくださいね。

はじめての補聴器は、病院または療育機関からの紹介の補聴器やさんから貸し出しを受けることができる場合が多いようです。
メーカーや機能の異なる複数の補聴器が揃っていますが、重度難聴はこのライン、高度難聴はこのライン、中等度軽度はこのラインと決まっているので、お子さんの聴力に応じた補聴器を選ぶことが大切になります。
補聴器を貸し出してもらっている間に、障害者手帳の交付手続きを進めるといいでしょう。
<障害者手帳の交付手続きの流れ>
市区町村の窓口で交付のための書類をもらう
↓
指定医師※に診断書・意見書を記載してもらう
※身体障害者手帳の診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条第1項の規定による指定医師に記載してもらう必要があります。お住まいの市区町村の障害福祉窓口に問い合わせしてください。
↓
申請書に規定の写真を貼り、診断書・意見書ともに市区町村の窓口に提出
↓
判定後、交付決定通知
障害者手帳の交付を受けたのちは、補装具として補聴器を購入する際に給付金がおります。福祉対応の補聴器は、自己負担一割で購入することができます。福祉対応以外の補聴器の場合は、差額を自己負担することになります。
乳幼児に補聴器を貸し出している補聴器やさんは、購入までの手続きに詳しいので相談されるといいと思います。
<補聴器の購入の流れ>
市区町村の窓口で申請のための書類をもらう
↓
指定医師から診断書・意見書を作成してもらう
↓
補聴器やさんで見積書をもらう
↓
上記書類3点と「補装具交付(修理)申請書」を市区町村の窓口に提出
↓
給付の決定通知が届く
↓
補装具費支給券の受け取り
↓
補聴器購入(一割負担)
ちなみに、補聴器に必須のイヤーモールドも給付制度があります。
こちらは、耳型をとって作るオーダーメイドなので、補聴器のように貸し出しは受けられません。手帳が交付される前の作製代は自費で負担することになります。イヤーモールド(片耳)で概ね1万円です。
お子さんが難聴だと分かったら、早めに障害者手帳の交付手続きを進めるといいですね。
また、地域によっては軽度中等度の難聴児も補聴器購入にあたり助成が適用されているところもがあります。市区町村の窓口で確認されることをおすすめします。