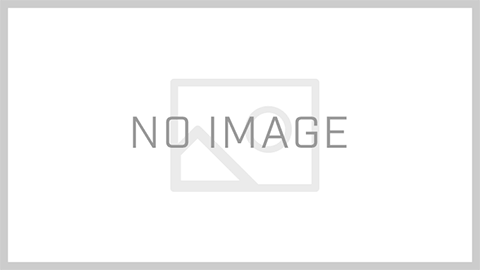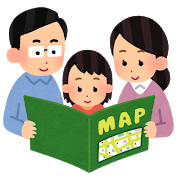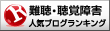難聴のお子さんは、病院や、聾学校などの療育施設、場合によっては聴こえの教室などの民間施設をかけもちして療育や言語訓練(ST)を受けていることが多いですよね。
息子は療育施設には通いませんでしたが、病院と聴こえの教室で言語指導を受けてきました。
そこであるのが、アドバイスされることがまちまちで、どっちを信じたらいいのかという問題。
これが難聴児の親を悩ます一番の種といっても過言ではないかもしれません。私も頭を悩ませました。
手話を併用しながら言葉育てをした方がいいのか、
聾学校へ行かないというのは間違っているのか、
セカンド手術は早い方がいいのか、
絵カードはたくさん作った方がいいのか、
絵日記は毎日書かないといけないのか、
集団生活はまだ早いのか、
ロジャーはいつから使ったらいいのか、
セカンド手術後はセカンドだけで過ごしたほうがいいのか、
など。
お世話になっている医師やSTの先生、親しくさせていただいている先輩パパさんママさんに相談しました。アドバイスは同じこともあれば、違うこともありましたが、どれも正しいように思えました。そして、体験談はとても勉強になりました。
また、ネットで調べたり、勉強会や講演会などに参加しました。いろんな考え方があるのだということが分かり、私にもできるだろうかと考えたりしました。
自分が決める
ロジャーの導入の投稿でも書きましたが、言語指導を受けていた聴こえの教室のSTの先生のアドバイスが、やはり息子のことを一番身近でよく知っていることから私はすんなり受け入れることが多かったです。
しかし、いつも信頼しているSTの先生に言われたままに実行していたかというと、そうではありませんでした。
セカンドの人工内耳手術後の過ごし方のことでした。セカンドの音入れからひと月後に保育園に入園という集団生活が待っていました。
STの先生は、
「保育園は二学期までは半日か、週半分くらいはお休みして、できるだけ静かな環境で音を聞いて過ごした方がいい」と言われました。また、
「早く慣れるためにセカンドだけで聞く時間を作るといいと思う」
とも言われました。
セカンドだけで保育園生活を送るのは絶対無理です。会話ができるほどまだ聞こえていませんでした。それに、保育園の入園に合わせて療育計画を立ててきたことを思うと、1学期を半分お休みするという選択肢はとても苦しいものでした。
そんな時、めったに相談しない医師に尋ねると、片側だけ鍛える感覚より両耳で聞く経験を積むことの方が大切だと教えてくれました。
そういうわけで、その時はそちらの考えに乗っかっちゃいました。
音入れ後からずっと両耳装用で保育園に行きました。数か月は、セカンド側の聴こえが邪魔して聞き返しや聞き間違いが多く、その中で集団生活が始まったのでそれは大変だったと思います。始めの頃はうるさくて聞こえないとよく言っていました。
しかし、夏休み前には気づくと聞き返しがなくなっていました。息子の中で両耳の聴こえにだいぶ慣れてきたのかなと感じました。
この選択が良かったかどうかは分かりません。もし同じような状況の方がいたら、家庭で過ごすという選択をする方もきっといらっしゃるでしょう。また、同じ悩みを相談されたとしても、こうした方が良いとは言い切れません。
子どものことになると深く悩みます。いろんなアドバイスや体験を聞いて迷います。迷いながら、思考錯誤しながら、子育てしていくしかないんですよね。
信頼している先生のアドバイスだとしても、まるっと受け入れずに、自分が決めた選択だという責任はどこかで忘れずにいることが大切なんじゃないかと思っています。
それで、かけもち療育の終着点ですが(笑)
当然ですが、オピニオンが多ければ多いほど迷うってことです。軸はどこに置くか決めておくと良いのかなと。多分、心の中で決まっているのでしょうけれど、迷いがあったり疑問があったら全てに相談することだと思います。療育の方向性は同じかどうか確認してみるといいのかなと。応援してくれる先生の言葉はモチベーションになります!