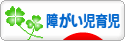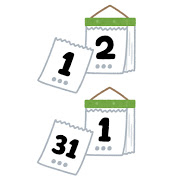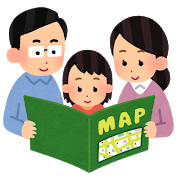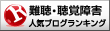子ども自身による補聴器や人工内耳の管理。
例えば、人工内耳だと、
- 外れた送信コイルを自分でつけることができる
- 電池切れを教えてくれる
- 充電池を自分で変えることができる
- イヤーモールドをプロセッサーに自分でつけることができる
- 自分で人工内耳のプロセッサーを耳にかけられる
- 異音や雑音から故障に気づく
- 寝る前に人工内耳を外して乾燥機に入れてセットすることができる
- 寝起きから自分で充電池を交換して人工内耳を装用することができる
ざっと挙げるとこんなことがあるかと思います(順不同)。
補聴器だと一番上を除いて、同じですね。
個々に成長も違えば、自立への向き合い方も違うので、一概に何歳までに何ができたらいいのかというのはないと思います。
突然できるようになることもあれば、その子の成長に合わせて教えてあげないといけないこともありますね。
でも、補聴器や人工内耳は大切なものなので、無理に子どもに扱わせて壊してしまっては大変なので無理はしないことだと思っています。
ただ、わが家の経験上、できれば小学校に通う時には、
学校に予備の電池を携帯し、充電がなくなった時は自分で電池を交換すること
はできるようにしていることをおすすめします。
以下のわが家の体験です。反面教師にしてください。
学校で充電がなくなった
一年生の10月でした。
昼前に担任の先生から電話がありました。
「人工内耳の充電が切れて聞こえないって言ってます。電池持ってきてくれますか」と。
そういえば、今朝電池を変え忘れたかも(当時は私がしていました)
慌てて学校へ行くと、3時間目の授業が始まる前で涙目の息子が。
その表情からかなり不安な思いをしたことが分かりました。
まず、片方のプロセッサーの充電池が1時間目の途中で切れたそうです。
その時点で先生には伝えたけれど、片方が聞こえるから大丈夫だと自分で判断したそうです。
そして、2時間目の体育が終わったところで、もう片方の人工内耳の充電も切れてしまったとか。
ちょうど休憩時間で先生に伝えたようです。先生はすぐに電話をくれました。
待っている間、先生は言葉を黒板に書いて伝えてくれたそうです。
黒板がすぐあったからいいものの、やはりいざという時の筆談用として、すぐに出せるメモと鉛筆をセットを持っていた方が良いと思いました。
そして、なにより、学校には毎日予備の電池を持っていくべきだと心から思いました。
自己管理について話し合う
帰ってから、まずは充電が切れてしまったことを先生にすぐに伝えられたことを褒めました。
でも次に同じことがあったら、今度はどうしたらいいか、ひとつずつ話し合ってみました。
1.人工内耳の充電がなくなったら自分で電池を変える
ボタン電池用のカバーとボタン電池をランドセルに入れて持ち歩くようにする
フル充電すると一日持つので予備の電池の必要性をあまり考えていませんでした。また、両耳装用なので片側の充電がたとえ切れても、もう片側が聞こえるので大丈夫だと甘く考えていました。
ここが一番の反省です。
自己管理という意味でもしっかり予備を自分で携帯する必要性を痛感しました。
携帯する電池ですが、充電タイプだと充電忘れをするおそれもあるので、ボタン電池にすることにしました。
しかし、息子自身は人工内耳のボタン電池を扱ったことがなかったので、電池式のカバーの付け方とボタン電池の入れ方から教えました。
充電がなくなった場合を想定して、一連の流れで何度か付け替えてみました。
そして、口頭でも順に説明させてみました。
電池は旅行用や緊急時や災害用にと思っていて、いつも私が付け替えていたのがダメでしたね。いざという時こそ自分でできるように慣れておくことが大事だと思いました。
2.聞こえない時は、筆談してもらう
筆談の紙と鉛筆を相手に準備させるのではなくて、自分で用意して書いてもらうように差し出す
そのために、今後はランドセルに筆談用のメモ帳と鉛筆を入れて持ち歩くようにしました。
また、学校ならいいけれど、話せると聞こえると思われることもあるから、「聞こえないので筆談してください」と伝えることが大切だよと話しました。
3.充電池の交換を自分でする
乾燥した充電池と充電器で充電した充電池とを毎朝自分で交換する
それまでは私が充電池を取り替えて、寝ている息子の耳に人工内耳をつけて起こしていました。過保護過ぎですね。
これからは目が覚めてから自分で充電池を交換するようにしました。
メンテナンスを見せる
今後はできることから自己管理を促していきたいです。
近頃はお風呂に入る前、自分で人工内耳を防水パック(アクアアクセサリー)に入れています。まだ時間はかかりますが、来年の夏のプールは自分でできるといいなと思っています。
他にも、プロセッサーのマイクカバーや乾燥剤の交換、消耗品の補充購入など、自己管理という意味ではまだまだ覚えるメンテナンスがありますが、マイクカバーの交換も私が勝手に交換するのではなくて、見せながら説明しています。
全部任せられるのはいつかな(*‘∀‘)

ブログ村のランキングに参加しています。読んだよ、とぽちっと押して頂けると嬉しいです。![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()